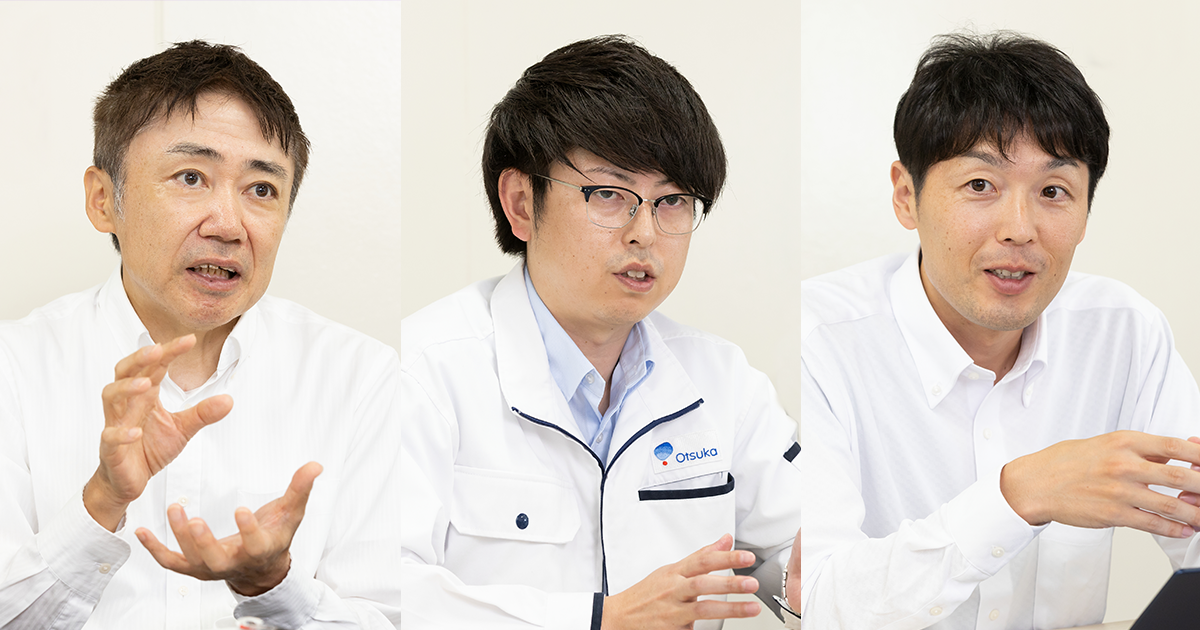徳島県鳴門市創業の日本における輸液のリーディングカンパニー
世界三大潮流の1つである鳴門海峡を臨む四国の玄関口、徳島県鳴門市。同所で1921年から事業を営むのが、大塚グループの発祥会社であり、日本の輸液のリーディングカンパニーである大塚製薬工場だ。同社は長きにわたって輸液事業に取り組み、同分野のリーディングカンパニーとして日本の輸液開発をけん引しつつ、近年では経口補水液「オーエスワン(OS-1)」が脱水症対策製品として定着するなど、医薬品、医療機器、メディカルフーズ(※)の分野で大きな存在感を示している。 ※同社は、医学的・栄養学的根拠を基に開発した医療の場で役立つ食品を「メディカルフーズ」と呼んでいる。
大塚製薬工場ではこの鳴門市の本社と工場を中心に、全国の工場・各支店合わせて約2300名の従業員が働いている。グループ創業の地である徳島に軸足を置きつつ、他方では海外でも事業を広げ、直近では新たに北米での事業強化を進めている。
新たなフィールドへと積極的に打って出る一方で、足元の社内では現在デジタルによる業務改革が進んでいる。特筆すべきは、現場の社員が積極的にデジタルを活用し、自らの業務改善にチャレンジしていることである。
「我々は地方の会社ですが、常に最新の技術情報をキャッチアップして取り入れています」と自信を持って語るのは、DXの取り組みを牽引するICTソリューション部部長の西上修次氏だ。長い歴史を有し、典型的な品質第一のモノづくり企業である同社において、デジタル時代のさらなる飛躍に向けてどのような取り組みが進んでいるのだろうか。
IT部門強化とデジタル環境整備でDX推進体制を構築
同社が本格的にデジタル化へ取り組み始めたのは、2019年のことである。経営テーマに「DX」と「スマートカンパニー」という文言が盛り込まれ、従来の情報システム室は部に昇格。攻めのITと守りのITの2つを軸とした体制への移行、これまで行われていなかった新卒採用も含むデジタル人材の強化など、さまざまな施策を進めた。
「特に大きかったのが人の採用。経営方針としてIT部門強化に舵を切っていただき、優秀な人材を継続的に獲得できるようになったことで部内に新しい風が吹き込み、しっかり守りながらも果敢に攻めることができる体制に移行することができました」と西上氏は振り返る。
これと同時に新たなIT製品の導入も強化した。Microsoft 365をベースとした業務基盤を確立し、RPA(Power Automate)、BPM基盤(intra-mart)、BI/データ活用基盤(Power BI)、ノーコード開発環境(Power Platform)を導入、従業員業務環境を改善して個々人がデジタル活用を促す仕組みを構築した。さらに最新の技術に対しても常に高いアンテナを張っていたことで、生成AIもいち早く導入。大塚ホールディングス契約のAzure OpenAI Service上に安全に生成AIを活用できる環境を構築し、データレイク(Microsoft Fabric)の構築を進めるなどデータを有効活用するための環境整備も進めている。
一貫して掲げてきたのが「内製力の強化」だ。開発をITベンダーに丸投げするのではなく、自社が知見を蓄えることで、業務部門からのデジタル化のニーズに素早く対応できるようにすることが狙いである。「内製力を高めた結果、俊敏性と外注時のコントロール力が備わりました。それによりDXの波に乗り遅れずに済み、コロナ禍の働き方の変化にも対応できました」と西上氏は話す。
製造委託先とのやり取りや情報管理が煩雑化
このようにデジタル活用において優れた取り組みを見せる大塚製薬工場だが、一方で業界特有の課題も抱えていた。同社の製品の中には製造委託によって生産する製品も少なくない。そのため当該の業務部門では、取引先とのメールの連絡やデータの送受信のやり取りによって業務が複雑化していたのである。
製薬メーカーは、GMP(医薬品の製造管理及び品質管理の基準)等への対応が必要であることから、特に監査証跡の観点を中心にさまざまな要件を満たしながら業務を遂行しなければならないが、同社では会社をまたぐメールのやり取りの業務に行き詰まりが生じていた。
「委託先がどんどん増え、製造販売・品質管理を含めて会社間を横断する情報のやり取りが増えました。業務改善に向けて各部門にヒアリングしたところ、社外と何往復もメールのやり取りがあって多くの無理・無駄が発生していました」と西上氏は明かす。
また部門ごとにも、それぞれの事情による課題も生じていた。例えば品質保証・品質管理を担当する信頼性保証本部 品質統括部では、製造ラインの変更管理などを行う品質イベント管理システムの老朽化による業務面で課題を抱えていた。当時の状況について、同部門にてIT領域を担当するQMシステム室 係長の沼田康貴氏はこう振り返る。
「旧来のシステムは他のシステムとの連携性がなく、医薬品業界で重視されるデータインテグリティにも弱い面がありました。業務では監査証跡や履歴を残しづらいという問題や、場合によっては改ざんとみられる操作ができてしまう懸念もありました。対外的な部分でも、メールのやり取りが煩雑なうえに最終的な原本を追いきれないという問題があったため、システムの刷新が必要だと感じていました」
製薬業界特有の業務課題にBusiness b-ridgeで対応
こうした業務部門が抱える課題の解決に向けて、BPM基盤上で業務プロセスフローの改善を行っていたものの、BtoBでの会社横断のプロセス改善は困難であったという。その中で西上氏の目に留まったのが、クラウド型業務システム構築ツールの「Business b-ridge」である。「Business b-ridgeには他の製品にない特色があった」と西上氏は語る。
「Business b-ridgeは私たちのような製造業に適した製品として、サプライチェーンにおける情報管理や製造委託先との情報管理、BtoBの業務プロセスをカバーする機能を有していました。詳細な権限管理はもちろん、製造工程における品質保証を規定したGMPや、製造販売業者における品質保証の基準を定めたGQPといった製薬業界向けの厳しいレギュレーションに対応できるシステムを構築できると判断しました」(西上氏)
品質保証業務に関する管理システムの内製化を実現
Business b-ridgeによって最初に着手したのは、医療機器の製造委託先とのコミュニケーションや情報を一元管理するシステムおよび、医薬品並びにメディカルフーズ関連の製造委託先との情報管理に使用するGMP・GQP対応のシステムだ。システム構築にあたっては、攻めのIT領域を担当するICTソリューション部のInternal DX推進担当 小林弘憲氏がBusiness b-ridge担当に任命され、業務部門と連携したアジャイル型の開発にて内製でシステム構築を進めていった。Business b-ridgeを扱った感想について小林氏は、「構築のしやすさ」を挙げる。
「市場にはさまざまなノーコード、ローコード開発ツールはありますが、複雑なことをするにはある程度コードを書けなければならないものも多い中で、Business b-ridgeは、私が担当するシステムにおいてはセキュリティ対策も含めてやりたいことを標準機能内で対応できました。それによって開発コストも抑えつつ業務効率化を図ることができました」(小林氏)
ツールの有用性に着目した同社は、新たに品質保証業務に関する品質イベント管理システムにBusiness b-ridgeを活用することを決定。前述した2システムに先駆けて最初にリリースされたが、この開発を主導したのは業務部門の沼田氏である。
「当初は医薬品製造業向けに特化したシステムを入れる予定でしたが、社内の基幹システムとのデータ連携が柔軟にできるものがありませんでした。そこでICTソリューション部に相談したところ勧められたのがBusiness b-ridgeでした。元々委託先とのシステムを小林さんと共同開発していてツールには触れていましたが、ベンダーに頼まなくても自社内である程度メンテナンスできそうで、長い目で見た時にメリットが大きいと感じました」(沼田氏)
Business b-ridge では、企業間横断の業務連携情報を、クラウド上で安全に一元管理可能
IT部門に頼り切りにならない業務部門起点のシステム開発
システム開発に当たっては、ICTソリューション部と同期を取りつつB-EN-Gの協力も得ながら現場主導で開発を進め、2024年1月に稼働を開始した。品質統括部では同システムのほかに、その後も小さな業務アプリケーションを内製で開発している。「なるべく自分たちでできるところは自分たちで対応し、システム連携やインターフェースの開発といった難しい部分はB-EN-Gに相談しながら開発を進めています」と沼田氏は語る。
現在は大塚製薬工場全体で、大小合わせ7つのBusiness b-ridgeベースの業務システムが稼働している。このうち、品質統括部だけで4つのアプリが稼働しており、さらに追加で5つのアプリ開発が進んでいる。現時点では品質統括部が先導する形だが、ICTソリューション部に頼らずに、業務部門だけでここまでデジタル化を進められるのは、Business b-ridge導入の大きなメリットの1つである。
「多額の費用を投じて、外部のベンダーへ開発を依頼せずとも、我々が主体となってBusiness b-ridgeを使ってどんどんデジタル化を進められるようになったことは大きな成果です」と沼田氏は語る。
Business b-ridgeが社内のデジタル改善基盤に
大塚製薬工場におけるBusiness b-ridge導入の効果については、まずは製薬メーカーにおけるGMP、GQPといったGxP対応のさまざまな業務システムを、大規模なパッケージ製品を導入することなく構築できるようになったというプラットフォームとしての側面が挙げられる。
具体的なシステム構築に伴う成果としては、「これまでのメールをベースとした非効率な業務の刷新に貢献しています。監査証跡として誰がどう操作したか履歴を時系列で追うことができる点や、社内外の関係者も含めて1つのプラットフォームで情報を管理できる点にも利便性を感じています」と西上氏は語る。
品質統括部における旧システムの課題だった基幹システム(SAP)やMESとの連携に関しても、データ連携ツールを介することで「One Fact, One Place」を実現。すなわち、データを一元管理して二重入力の問題を解消するとともに運用性の高い仕組みを実現している。
またICTソリューション部の視点では、先般の沼田氏のケースのように、業務部門から業務のデジタル化の相談があった際に新たな提案の引き出しができ、大きなコストをかけずに各々のニーズへ対応できる仕組みが整ったことも大きな成果だ。
アプリケーション開発ツールの運用にあたっては内製化がポイントになるが、大塚製薬工場では内製開発の体制を構築しつつ、同時に新たな保守ベンダーの育成も進めている。同社はBusiness b-ridgeを自社で習熟したうえで、パートナーである地場のシステム開発会社へスキルを伝授。これにより、開発および保守体制の強化を図っている。
一方で、社内では闇雲にはBusiness b-ridgeの技術者を増やさない方針とし、しっかりとガバナンス面も考慮している。これらの形は、システム開発を丸投げしてブラックボックス化に陥ったり、現場に主導させすぎた結果として「野良アプリ」が増えて担当者がいなくなった際にデジタル負債化してしまったりするという、よくあるIT導入時の失敗例とは無縁の取り組みといえるだろう。
「デジタルに挑戦したい人」が最大限に力を発揮できる会社
企業のDXは、ITツールを導入するだけで進むとは限らない。大塚製薬工場におけるデジタル化の取り組みを社内に定着させている重要な要素が、ICTソリューション部からの積極的な広報・啓蒙活動だ。社内イントラ上でPower BIやBusiness b-ridgeで実現した業務改善事例を従業員に向けて発信したり、ツールの講習を行ったり、事業部が実施する部会にも必要に応じて参加しデジタル化の事例を共有している。こうした機会を通じて、各部門のニーズを汲み取りつつ、デジタル化のカルチャー醸成を図っている。
こうしたデジタル化の情報発信に対し、社内では特に各部の若手からの関心が高いという。「例えば、Power BIに関するトレーニングを告知すると、応募が殺到してすぐに募集枠が埋まることもあります」と小林氏は語る。上層部に対しても生成AIフォーラムを開催したり、役員向けのChatGPTのマンツーマン講習をICTソリューション部の若手が担当するといった仕掛けも行われているという。
近年同社では、「フラットな風土」というキーワードを重視しているが、まさにデジタル化の活動においてその考え方が明確に反映されている。ICTソリューション部と各部との距離や関係性が近く、部のフロアに他部署の社員が気軽にデジタル化の相談にきて、コミュニケーションを取っている。「業務部門にいても、やる気次第でどんどん新しい技術に触り、自分で自分の仕事をスマートなものに変えていける自由度があるのが大塚製薬工場です。部門を問わず、デジタルに興味がある人にとって良い環境が整備されています」と西上氏は胸を張る。
デジタル化への意欲を引き出す「2階建て構造」
こうしたデジタル化を進める同社を、西上氏は「2階建て」と表現している。1階のICTソリューション部がデジタル活用の道具立てを揃え、安全なインフラを整備し2階のビジネス部門を支える。各部門のデジタル化推進人材は何かあれば1階に降りてきて相談し、業務のスマート化を進めていく。こうした連携関係の構築と距離の近さが同社のデジタル化の特徴だ。これによって適切な統制のもとで業務部門の自主的かつ最適なデジタル化が進められ、同時にシャドーITや個別最適化のリスクを回避している。「そのためにも、ICTソリューション部が新たなテクノロジーの目利き力を身に付け、継続的にスキルを習得していく必要があります」と、1階の住人である小林氏は襟を正す。
一般的に大企業では、やりたいことがあっても社内調整の難しさや検討段階が長引くなどの理由から、業務改善に向けた良い話が潰れてしまうことが起こりがちだ。だが、同社では2階建ての仕組みによってすぐにベータ版としてアウトプットを出し、アイデアをすぐに形にして取り組みを前進させられるデジタルの土壌が備わっている。そこには、素早い開発ができるBusiness b-ridgeも貢献している。
今後のデジタル活用に関して西上氏は、「急速に進化するテクノロジーを全社の業務プロセスにしっかり組み込んでいくことにこだわっていきたいと思います。日常業務の改善にとどまらず、最終的にはビジネスの課題解決につなげていくことを目指しています」と語る。併せて、Business b-ridgeを扱える人材育成も強化していく構えだ。
コロナ禍を境に国内企業ではDXの動きが加速したが、最初に大きく構えつつもその後の活動は尻すぼみになっているケースも少なくない。そのような中で大塚製薬工場では、ICTソリューション部が最新の技術へアンテナを張り、社内へ主体的に情報発信しつつ業務部門のデジタル化のニーズに真摯に応えながら、着実に一歩ずつDX化の歩みを続けている。
※本記事は2025年11月現在の内容です。
※本記事中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載当時のものであり、変更されている可能性があります。
※掲載企業様への直接のご連絡はご容赦ください。